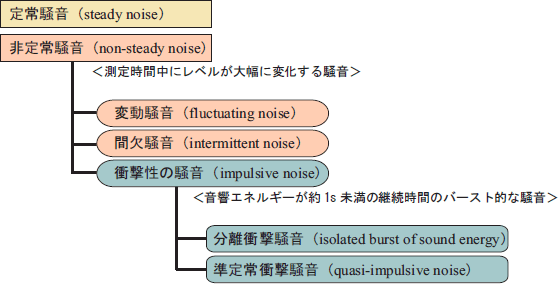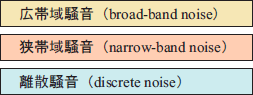1. 音とは
音とは、一般に気体、液体、固体などの媒質中を伝搬する波(音波、弾性波)ですが、本冊子では、主に空気中を伝わる音波に関して説明します。
音波は、毎秒約 340 m の速さで伝わる波動現象です。我々は、空気中を伝わる波動を耳によって聞いています。この波動は、空気の大気圧の圧力変動(交流的な圧力変化)が連続的に生じることによって発生します。
一般に、大気圧(静圧)からの圧力変動を音圧と呼んでいますが、JIS 規格 JIS Z 8106:2000(音響用語)から引用すると;
● 瞬時音圧(instantaneous sound pressure) |
媒質中のある点で対象とする瞬間に存在する圧力から静圧を引いた値 |
● 音圧(sound pressure) |
特に指定しない限り、ある時間内の瞬時音圧の実効値 |
と、「瞬時音圧」と「音圧」とを明確に分けております。
(右図 1-1.を参照)
ただし、本冊子では、今まで通り、「音圧」という言葉で、上記の2つの用語を適宜使い分けておりますので、あらかじめご了解ください。
聴力の正常な若い人の聞くことのできる音圧の範囲は、20 μPa 〜 20 Pa です。μ は、「マイクロ」と読み、10-6 を意味する補助単位です。従って、最も大きな音と小さな音の音圧の比は、106にもおよびます。また、“Pa”(パスカル)は、圧力の単位で、1 Pa は 1 m2 の面積に 1 N(約 0.1 kg 重の重量に相当)の力を加えたときの圧力に相当します。天気予報の大気圧は、その 100 倍の大きさの hPa という単位を使用しています。(気圧という言葉は、単位としても使われており、1 気圧は、約 1013 hPa に相当します。)
音の強さと同様に、聴力の正常な若い人の聞くことのできる瞬時音圧の周波数範囲は、約 20 Hz から 20 kHz と約 1000 倍の範囲となります。厳密な区別ではありませんが、音の周波数範囲は一般に下記に分けることができます。
| 20 Hz 以下 | :超低周波音(infrasound) |
| 20 Hz 〜 20 kHz | :可聴音(audible sound) |
| 20 kHz 以上 | :超音波音(ultrasound) |
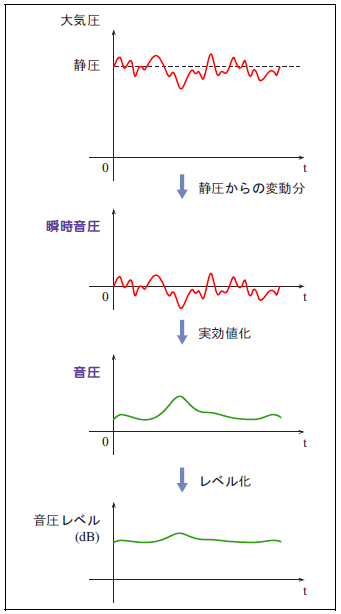
図 1-1 騒音計の基本的処理フロー
私達は、音を耳で感じるとき、次のような音の特徴から音の違いを聞き分け、判断しています。
● 音の高さ :
私たちが高い音、低い音といっているもので、音の周波数の違いから起こります。 同じ「ア」の音声でも、高い声の「ア」と低い声の「ア」がありますが、これは、「ア」としての音の波の形は同じでも、周波数が異なるためで、周波数が高い音はかん高く、周波数の低い音は低く・重々しく聞こえます。
● 音の大きさ:
同じ音の高さの「ア」と言う声でも、大きな声の「ア」と小さな声の「ア」があります。これは、同じ様な波形をしていても、大きな声の「ア」は振幅が大きく、小さな声の「ア」は振幅が小さいことによります。騒音計は、この音の大きさを測る測定器です。
● 音色・音質:
私たちは、同じ音の大きさ、同じ音の高さで弾かれている楽器の種類を聞き分けることができます。これは、楽器からでてくる音の音色や音質を聞き分けているのです。音色や音質は、現在でも十分には解明されていませんが、音の波形が微妙に異なることによるといえます。
また、音は波としての性質を持っていることから、「反射」、「透過」、「回折」といった性質を持ち、距離によって減衰します。以下に図示しましたので参考としてください。
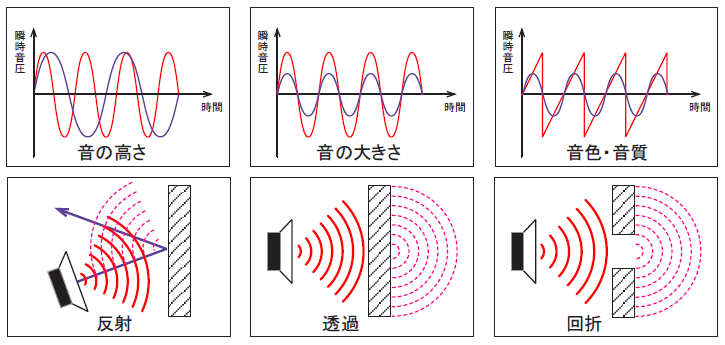
図 1-2 さまざまな音の特徴と性質 |
2. 騒音とは
騒音は、さまざまな音の中で「聞きたくない不快な音」、「邪魔な音」の総称です。前出した音響用語規格(JIS Z 8106:2000)によれば、騒音(noise)は “不快なまたは望ましくない音、その他の妨害” と定義されています。不快と感じる音は、健康や生活環境に係わる被害を生じ、やがて公害問題に発展します。
騒音の評価においては、可聴音である 20 Hz 〜 20 kHz の範囲のうち、主要な帯域である 50 Hz 〜 5 kHz ぐらいを対象とします。なお、普通の会話では、300 Hz 〜 3 kHz の範囲が聴取にとって重要となります。
大きな騒音の中で長時間働いていると難聴になったりしますが、こうした騒音から人の生活を保護するために法律によって騒音の規制が定められています。
騒音を測定評価する測定器として一般的に騒音計が使用されています。音を数値化して表す方法として、物理的尺度と感覚的尺度があります。
物理的尺度としては、
① 音圧レベル(sound
pressure level)、
② 音の強さのレベル(sound intensity level)、
③ 音響パワーレベル(sound
power level)、
およびこれらを周波数分析したオクターブバンド、1/3
オクターブバンドレベルなどがあり、
感覚的尺度としては、
④ 音の大きさ(loudness)、
⑤ 音の高さ(pitch)、
⑥ 音色(timbre)、
⑦ 音の大きさのレベル(loudness
level)、
⑧ 騒音レベル(A weighted sound pressure level)等があり、
その多くは JIS
や、IEC(国際電気標準会議)などで定義されています。特に感覚尺度では現在様々な評価量が研究発表され今後ますます発展する分野となっています。
環境騒音では騒音レベルを、商品開発では音響パワーレベルや 1/3オクターブ分析、最近では音質評価パラメーターを測定するなど、それぞれ測定目的に適した測定項目で評価されています。これらの概要は 5 章、6 章、および 11 章にまとめましたのでご参照ください。
騒音計は、この中の ① 音圧レベル、⑧ 騒音レベルを測定する計器に当たり、最近の技術進歩によりそれらのオクターブバンド、1/3 オクターブバンドレベルや、④ 音の大きさ(ラウドネス)をも測定できる機種も発売されています。
それでは騒音に関してもう少し詳しくみてゆきましょう。
図 2-1 は環境騒音の種類とその大きさの例を示したものです。
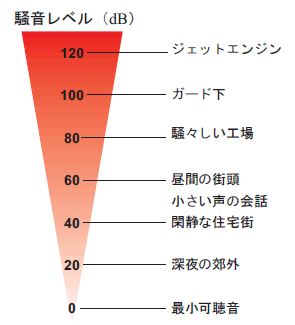
図 2-1 いろいろな騒音とその大きさ(レベル)
3. 騒音の分類
騒音の変化には、大きく分けて「レベルの時間軸上における変動」と、「周波数軸上におけるスペクトル成分の違い」があり、これを基に騒音を分類することができます。
| (注意)
この章は、JIS Z 8733:2000 附属書 F(参考)「騒音のスペクトルおよびレベルの時間変動による分類」を引用しております。 |
3-1 レベルの時間変動による分類
騒音は、レベルの時間変動という観点から、下記のように分類されます。
|
|
各タイプの特徴と典型的な時間軸波形は次の通りです。
● 定常騒音(steady noise)
測定点において、ほぼ一定レベルの騒音が連続しており、騒音計の指示値に変動が無いか、または多少変動しても変動が僅かである騒音を定常騒音といいます。
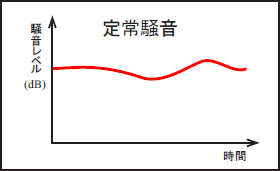
図 3-1
● 変動騒音(fluctuating noise)
測定点において、騒音レベルが不規則かつ連続的にかなりの範囲にわたって変動する騒音を変動騒音といいます。 例えば、ある程度の自動車交通量を有する道路の近くで観測される騒音は、ほとんどの場合変動騒音です。
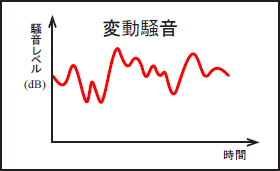
図 3-2
● 間欠騒音(intermittent noise)
ある時間間隔をおいて間欠的に発生する騒音の内、発生時毎の継続時間が数秒以上の騒音を間欠騒音といいます。一つの発生から次の発生までの時間間隔は、ほぼ一定の場合もあれば、列車や航空機の通過のように不規則な場合も有ります。
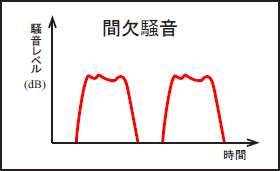
図 3-3
● 分離衝撃騒音(an isolated burst of sound energy)
例えば、パイルハンマが杭を打つときの音のように、個々の騒音が分離できる衝撃騒音を分離衝撃騒音といいます。分離衝撃騒音は、単発の場合もあり、間欠的に発生する場合も有ります。また、発生毎のレベルがほぼ一定の場合や、かなりの範囲にわたって変化する場合があります。
通常はバーストの間隔が 0.2 s
以上のものを言います。
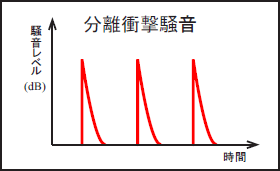
図 3-4
● 準定常衝撃騒音(quasi-steady impulsive noise)
例えば、ベルや削岩機のように、ほぼ一定レベルの衝撃音が極めて短い時間間隔(約 0.2 s 未満)で繰り返して発生する騒音を準定常衝撃騒音といいます。このような騒音は、感覚的には定常騒音として受け取られることが少なくありません。
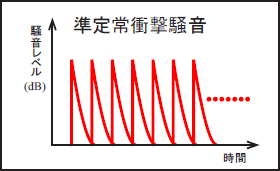
図 3-5
3-2 周波数スペクトル形状による分類
騒音は、周波数軸上におけるスペクトル形状という観点から、下記のように3つのタイプに分類されます。
|
|
各タイプの特徴と典型的なスペクトル波形は次の通りです。
● 広帯域騒音(broad-band noise)
音響エネルギーが比較的広い周波数範囲に分布するスペクトルを有する騒音です。
例:滝の音、エアコン送風路からの排気音、高速道路騒音など。
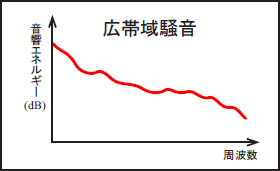
図 3-6
● 狭帯域騒音(narrow-band noise)
音響エネルギーが比較的狭い周波数範囲(1/3 オクターブバンド以内)に集中するスペクトルを有してかつ離散的な音を含まない騒音です。
例:遠雷の音(低周波)、草原や渓谷を吹き抜ける風の音(中程度の周波数)、自動車のタイヤの空気が抜ける音(高周波)など。
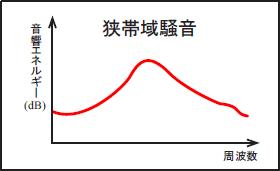
図 3-7
● 離散純音(discrete tone)
ピッチの感覚をもたらす周期的な音圧変動を持ち、周波数的にはラインスペクトルを有する騒音です。
例:ファンのハム音、デジタル機器からのビープ音、楽器音など。
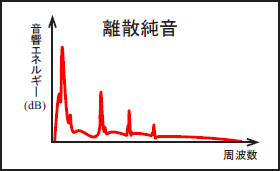
図 3-8