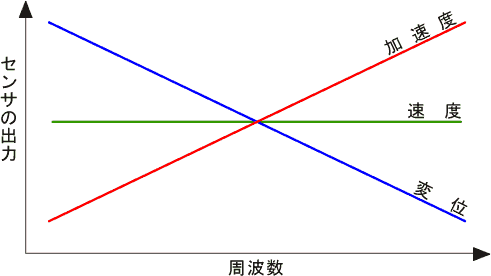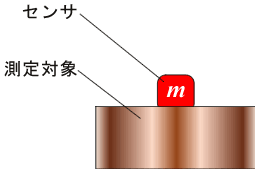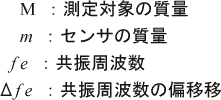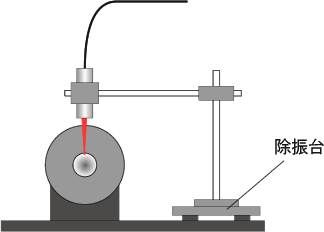1.振動とは
振動はその特性において次の3つに大きく分類することができます。
●直線振動
●曲げ振動
●ねじり振動
また、こうした振動を定量的に捕らえるためには、一般に次の3つの物理量が使用されます。
| ●変位(単位:m) ●速度(単位:m/s) ●加速度(単位:m/s2) | 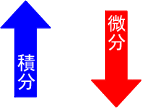 |
各物理量は上に図示したように、微分乃び積分することでそれぞれ相互に変換することが可能です。 速度が周波数に対して一定である場合、変位並びに加速度の周波数に対する出力の特性をグラフにすると、一般的に次の表のように表わされます。
|
|
この表からは、次のことを読み取ることが出来ます。
周波数の低い範囲では変位の感度が高く、周波数が上がるにつれて速度へ、また加速度へと移って行く。 |
このことから、周波数の低い場合は変位で、周波数が高い場合には加速度で測定した方が、一般的には感度よく測れることになります。
設備診断等では、数百Hzまでは変位・速度で、それ以上の周波数では加速度で測定します。
2.振動センサーの選択について
精度よく振動を検出するための適切なセンサーを選択するためには、次の点を考慮する必要があります。
● 対象とする物理量は何であるか
◆変位
◆速度
◆加速度
● 測定対象物の大きさ
センサーには、接触式と非接触式のタイプがあります。接触式センサーを使用する場合には、質量効果(後述)について、また、接触・非接触に関わらず、センサーの測定必要面積 S と対象とする測定物の面積 S'について考慮する必要があります。(S'/S>1でないと正確な計測は不可能です。)
● 対象物の振動の大きさ、周波数範囲
測定対象の振動の大きさ、周波数範囲のおおよその目安を求めておく必要があります。ここでの目安を誤ると、場合によっては、センサーを破損する可能性があります。
● 測定環境 測定対象並びに周囲環境の温度、湿度や、埃、油、水の存在の有無をチェックします。
測定方式によって得手・不得手があります。
以上をチェックした後、測定対象に最適なセンサーの選択に入ります。当社製品での対応を以下表にまとめてみましたので参考としてください。
| 測定方式 | 静電容量式 | レーザードップラ式 | 圧電素子 | 電磁式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品型名 | VEシリーズ | LVシリーズ |
NP-2000シリーズ (電荷出力) |
NP-3000シリーズ (アンプ内蔵) |
MPシリーズ |
|
| 非接触測定 | ○ | ○ | ||||
| 分類 | 直線振動 | ○ | ||||
| ねじり振動 | ○ | |||||
| 物理量 | 変位測定 | ○ | ||||
| 速度測定 | ○ | ○ | ||||
| 加速度測定 | ○ | ○ | ||||
| 周波数 | 低周波 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高周波 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| 超高周波 | ◎ | |||||
| 振幅 | 大振幅 | ○ | ||||
| 微小振動 | ◎ | ○ | ○ | |||
| 環境 | 高温環境 | ○ | ||||
| 粉塵 | ||||||
<接触式と非接触式選択の際の注意点>
▼接触式
| ■優位点 |
|
| ■注意点 |
質量効果 |
質量効果とは、測定を行うために取付けたセンサーの質量により測定対象体の固有振動数が影響を受け変化してしまうことを言います。
|
|
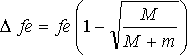
|
物体の固有振動数は、物体の質量により変化するため、センサーを取付けると、センサーの質量が物体に付加され固有振動数が小さくなります。従って、測定対象体の質量に比べセンサーの質量が十分に小さくないと固有振動数を変化させることになり測定誤差となります。 上図のように被測定物の質量を M、センサーの質量を m、測定系の固有振動数を fe とすると図中の式から固有振動数は Δfe だけ減少します。センサーの質量としては被測定物の質量の 1/50 が目安になります。質量 m が M の 1/50 の時、振動数の変化率 Δfe/fe は、0.01 となります。なお、ここでいう質量は測定対象全体の質量ではなく、センサーを取付ける部分の構造体の質量となり、意外と軽い場合が有りますので注意が必要です。
▼非接触式