計測機器システム構成例・活用事例
環境・インフラ
精密建物の実稼動解析
精密実験棟(特に音や振動を扱う建物)では、空調などの付帯設備から発生する音や振動が問題となることがあります。そのため、振動源となる付帯設備の設置は、音や振動が伝わらないように実験室からなるべく離れた場所を選び、さらに振動絶縁、遮音対策を施しています。実際にその対策がうまくいっているかどうかは、付帯設備を稼動状態にした上で振動を測定・解析して評価します。このとき、振動伝播に着目した評価として、どのような振動(挙動)がどのくらい絶縁されているのか(あるいは伝わっているのか)を解りやすく視覚的に表現する方法があります。それが、実稼動アニメーションです。
ここでは、弊社音響棟(Acoustics Lab)の解析例を紹介します。解析の目的は、屋上に設置した室外機から発する振動が精密測定を行うエリアへ与えている影響を調べることです。屋上平面上の22点(基準点×1、測定点×21)に加速度検出器を設置し、実際に設備を稼動した状態で振動の計測を実施しました。
建物の振動解析の場合は低周波・高感度型の加速度検出器が必要なため、振動レベル計 VR-6100* や、そのセンサー部(NP-7310)を使用しています(図は、VR-6100* を使用した例です)。
* VR-6100は販売終了いたしました
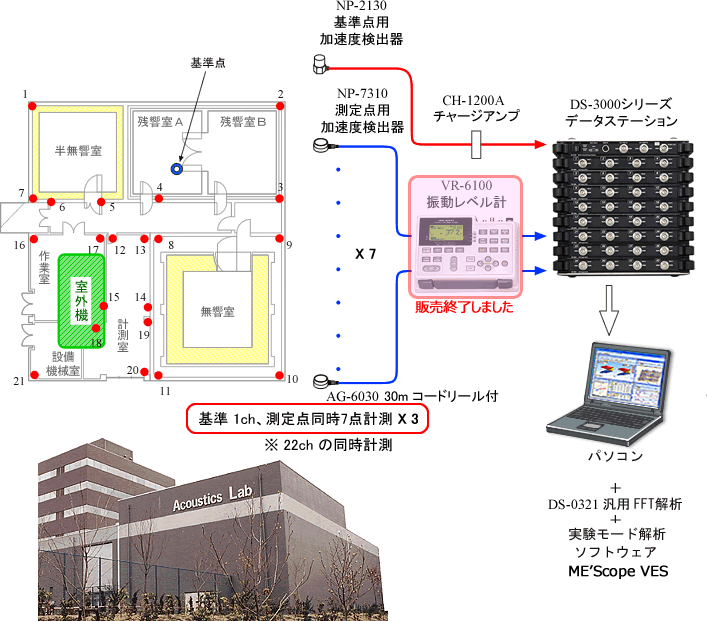
機器構成
| 型名 | 品名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
1 |
DS-3000シリーズ |
マルチチャンネルデータステーション | 24 ch FFT(基準 1 ch、測定点同時 7 点計測× 3 回) |
| 2 | DS-0321 |
汎用 FFT 解析ソフト | FFT 解析ソフト |
| 3 | MEscope | 実験モード解析ソフトウェア |
実稼動解析、実稼動アニメーションソフト |
| 4 | NP-2130 | 加速度ピックアップ | 1 台、基準点測定用 |
| 5 | VR-6100 |
振動レベル計 | 7 台、建物の振動解析の場合は低周波・高感度型を使用 |
| 6 | CH-1200A | チャージアンプ | 1 台(基準点測定用) |
| 7 | AG-6030 | 延長ケーブル | 必要数 (延長 30mコードリール付) |
解析方法
- 1. 解析する建物のモデル(形状)を定義する(MEscopeVES 使用)
- 2. 解析する建物の基準点を設定する
- 3. 基準点(固定点)と測定点(移動点)のパワースペクトルとクロススペクトルを測定し、同時に DOF(自由度)を記録する
- 4. 得られたデータから、ODSFRF を計算する(ME’scopeVES を使用)
- 5. アニメーションする(MEscopeVES 使用)
解析データ例
建物のモデル(形状)
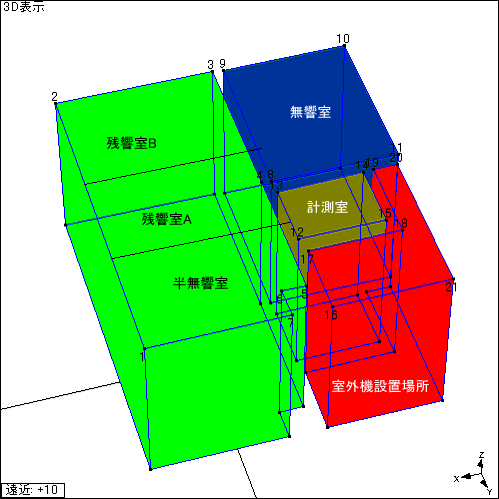
実稼動アニメーションを行うためには、振幅と位相データが必要です。
この振幅データは、一点固定の基準点を含む各測定点のパワースペクトルを測定することで得ることができます。
また、位相データは、基準点と各測定点のクロススペクトルを測定することによって得ることができます。
それぞれ得られた振幅と位相を合成し、アニメーションするためのデータ(ODSFRF)が作られます。
(※ODSFRF:位相付きパワースペクトルのようなもの)
屋上における室外機の振動(ODSFRF)
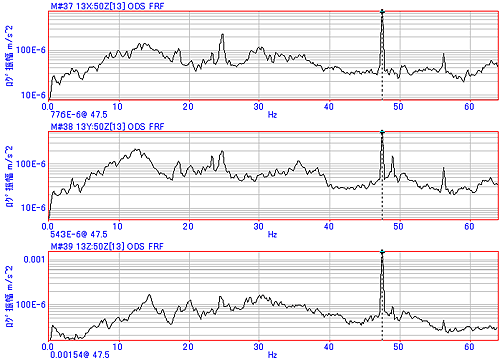
上段から XYZ方向のデータ(測定点13)
ODSFRF の一例です。室外機の回転振動の影響で、建物の振動に約 47.5 Hz の急峻なピークがあるのがわかります。
この振動が精密測定を行うエリアへ伝わっているかどうかの実態を把握するために、測定点ごとの振幅と位相情報を合わせて比較します。
結果、振幅の大小だけではなく測定点間でどの様に変形(動的に)しているのかを知ることができます。ただ、複数の測定点について振幅と位相情報を同時に計測し、
変形までを把握するというのは容易ではありません。このように多くの情報を用いて評価対象の建物全体の動的な変形を把握するためには、
実稼動アニメーションを利用することをお勧めします。
アニメーション
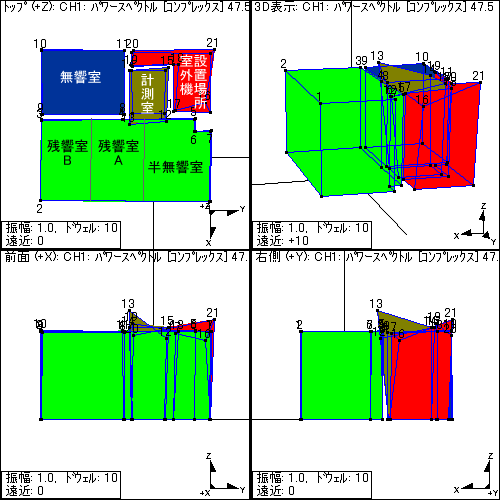
>左上:上面(Z方向) 右上:3D 左下:X方向 右下:Y方向
3つの面と立体的に見た変形を視覚的に捉えることで、室外機が設置されているエリアとその隣のエリアは大きく変形しているにもかかわらず、精密測定エリアは殆ど変形していないことがわかります。
また、万一振動問題が発生していることが見つかったとしても、実稼動アニメーションによって変形状態が把握できることで、対策の指針が立てやすくなります。
実稼動アニメーション
ポイント
- FFTアナライザー側の使用ウィンド関数は基準点用および測定点用加速度ピックアップ信号とも“ハニングウィンドウ“を使用する。
- FFTアナライザーの周波数レンジは、回転機器の回転速度(今回の場合は室外機)などから見当つけて決定する。
- FFTアナライザーのダイナミックレンジを有効に使う様に設定するが、A/Dオーバをさせてはいけない。
- FFTアナライザーの平均化回数はスペクトルの安定の程度で設定する。
- サンプル点数によってクロススペクトル、パワースペクトルのライン数が決定される。
一回に取り込むデータのサンプル点数が多くなると、ライン数も増加して周波数分解能が高くなる。
自社の設備や測定ツールを利用した、自動車の評価試験や音響・振動試験(出張測定含む)をお引き受けします。
また、お客様の困り事や課題に対するコンサルティングもお引き受けします。 課題設定から、現象把握、効果確認まで、お客様の解決プロセスをご支援します。
詳しくはこちらのページを参照ください。
