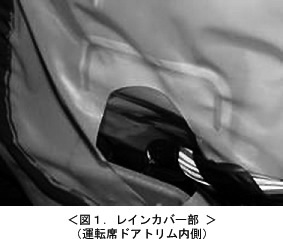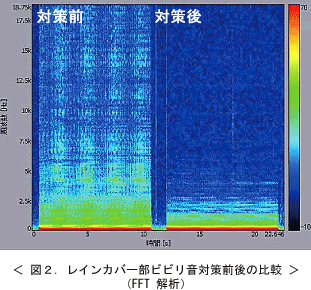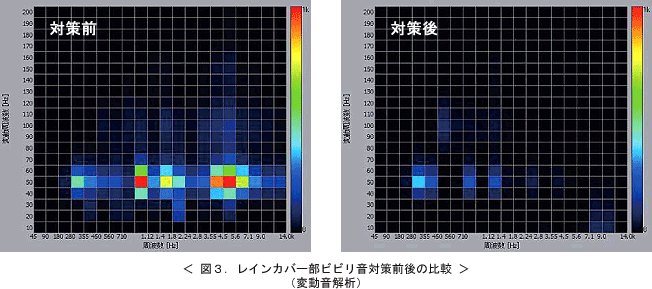計測機器システム構成例・活用事例
くるま開発
変動音解析による車両ビビリ音評価
自動車業界において、ラウドネスをはじめとする音質評価指標は現在幅広く浸透し、様々な分野で人間の聴感上の印象を定量化する技術として用いられています。特に最近では、時間変動成分に起因した音色評価、あるいは異音検出の話題が多くなっています。
これを検出する一般的な指標としてはラフネス,変動強度がありますが、いずれも特定の時間変動成分のみを抽出する指標となっています。しかし、工業製品から放射される機械変動音は様々な変動周期を含んでいる事もあり、その特徴量を抽出するのには不十分であることが少なくありませんでした。そこで、ラウドネスをベースとした様々な時間変動成分を定量化できる指標(変動音解析)を用いる事で、音の音色(高低)のみならずその時間変動周期も定量化する事ができるようになります。
本例では、車載オーディオを一定以上の出力で再生した際に、主として低音域で再生される信号に共振して発生するビビリ音(車両に何らかの振動が加わった時に、車室内の特定箇所が共振し、パーツ同士が触れ合って発生するノイズ) について解析した事例を紹介します。
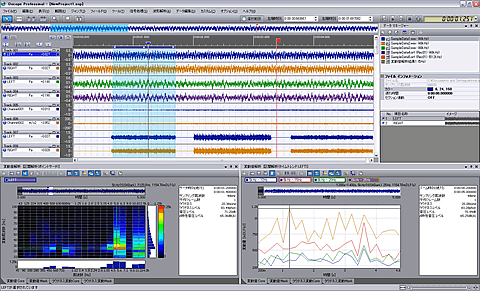
測定システム

機器構成
| 型名 | 品名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DS-3000シリーズ | データステーション | Max 32 ch |
| 2 | LA-7500 | 精密騒音計 | 周波数範囲:10 Hz〜20.0 kHz |
| 3 | OS-2760 | Oscope 変動音解析パック | 「ラウドネス」「シャープネス」「ラフネス」 「変動強度」「AI」「トーナリティ」の6つの物理量を可視化 |
| 4 | パソコン |
測定データ例
|
|
図3には同じ音源について、対策前後の変動音解析結果を示します。対策前は変動周波数(縦軸)が 50 Hz で、音の高さ(横軸)が 1 kHz、1.5 kHz、5 kHz 付近を交差する升目の変動量が大きくなっているのに対し、対策後は着目した升目の変動量が小さくなっていることがわかります。対策前後の変動量としては約 97 %減と大幅に減少しています。
|
|
従来の FFT 解析と比較して、変動音解析は音の変動量にフォーカスすることでビビリ音の定量化が可能になります。対策前後の効果も数値表現できるため、設計の標準化にあたり非常に効果的であると考えられます。
この事例では、更に検討を進め、今後ビビリ音評価/ 対策の判定閾値設定(設計標準化)、およびビビリ音発生源の特定(設計効率化)を検討しています。
設計標準化については、ある変動周波数/ 周波数に対し、どの程度の変動量を 抑えれば良いかを定めること、設計効率化については、変動周波数/ 周波数のマッピングから発生箇所を特定すること、各々についての可能性について進めています。
応用例
- 自動車エンジンの音色評価
- トランスミッションの異音評価
- 複写機作動音に混入する異音検出
自社の設備や測定ツールを利用した、自動車の評価試験や音響・振動試験(出張測定含む)をお引き受けします。
また、お客様の困り事や課題に対するコンサルティングもお引き受けします。 課題設定から、現象把握、効果確認まで、お客様の解決プロセスをご支援します。
詳しくはこちらのページを参照ください。
最終更新日:2017/12/14