計測機器システム構成例・活用事例
材料・素材
セラミックプレートの内部クラックの検出
セラミックプレートの表面および内部クラックの発生による良品・不良品の判別を周波数解析により行います。
セラミックプレート試料をその試料が自由振動に近くなるように柔らかなスポンジの上に置き、インパルスハンマで打撃し、加振信号と、その時に発生する打音をマイクロホンで捉えます。加振信号と発生打音信号の両信号をFFTアナライザーに入力し、発生音信号を加振信号で正規化演算して、周波数解析を行います
測定システム

機器構成
| 型名 | 品名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
4 |
DS-5000 / O-Solution | 3ch 40 kHz FFTセット | ◆DS-5100メインユニット ◆DS-0523 3ch 40 kHz 入力ユニット ◆OS-5100 プラットフォーム ◆OS-0522 FFT解析機能 ◆OS-0512 ハードウェア接続機能 |
2 |
MI-1235 | 計測用マイクロホン | |
3 |
MI-3111 | マイクロホンアンプ | |
4 |
GK-3100 | インパルスハンマキット | アンプを含む |
測定方法
- 1. 測定対象物が自由振動するように、柔らかいクッションの上に置くか、あるいは宙吊りとする。
- 2. 測定対象物をインパルスハンマで打撃し加振波形を測定する。
- 3. インパルスハンマの打撃音をマイクロホンで測定する。
- 4. 加振波形と打撃音波形より周波数応答関数を求める。
解析データ例
中央加振
セラミックプレートの打撃の条件として、床面の接触を安定させるために 15 mm 厚のスポンジを使用しています。
初めに、正常なセラミックプレート打音の周波数解析を行います。今回の試験では、加振点を中央並びに端点にとって測定を行いましたが、周波数応答関数のピーク値は周波数約 5 kHz (5.3kHz)に集中していることが求められています。
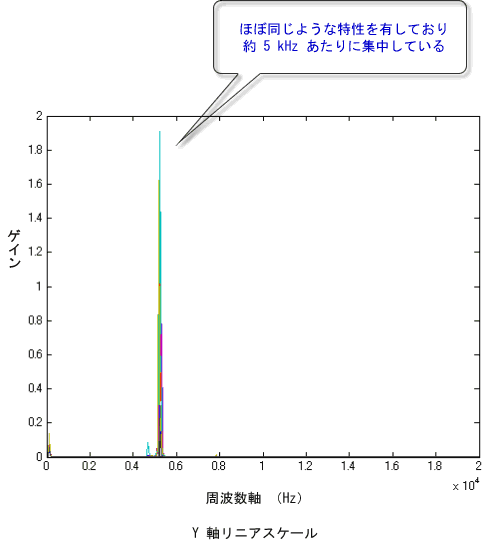
端点加振
次に、不良品のセラミックプレートの打音の周波数解析を行います。不良品の打音の周波数は正常なものに比べ、周波数応答関数のピーク値に周波数軸上ばらつきがあり、かつそのピーク値そのものも低くなっています。
また、加振点を中央並びに端辺にとって打撃しても同等の結果が得られたことから、この不良品は、表面または内部に何らかの欠陥を有しており、このため剛性が低くなっていると考えられます。
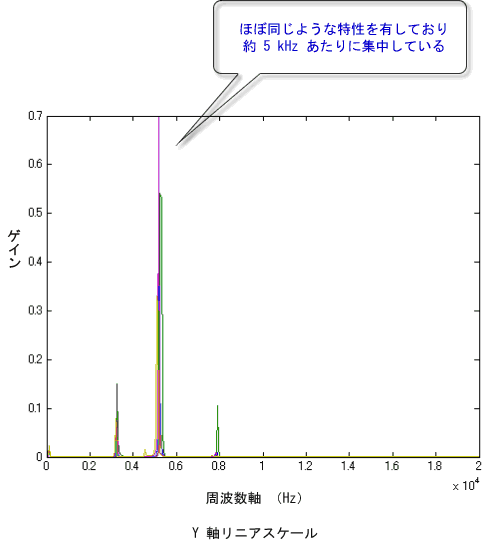
中央加振
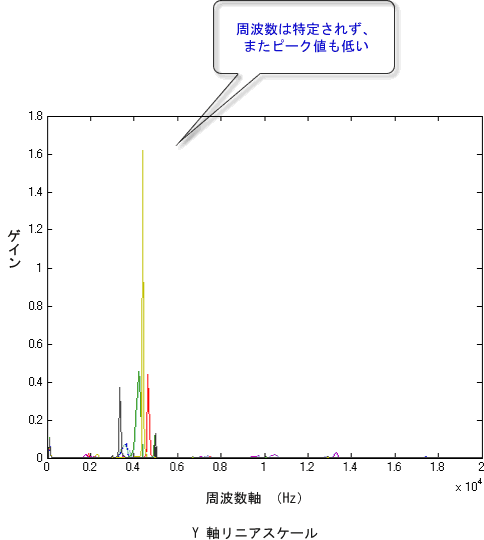
端点加振
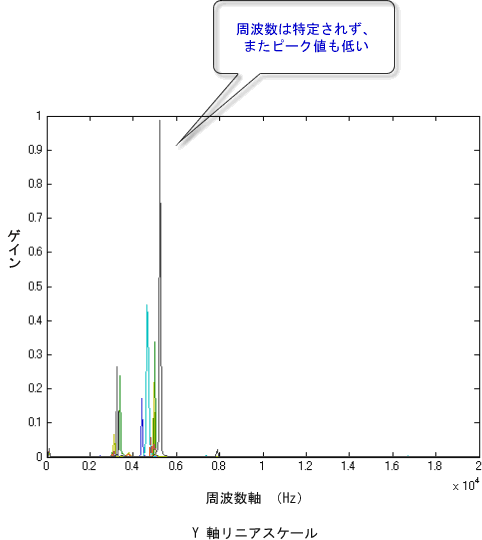
通常、内部に欠陥を有する場合、聴感上鈍い音となりますが、これは減衰が大きいことを示しています。ただし、この減衰は微妙なことが多く、聴感上で定量化することは困難です。
応用例
- ブレーキディスクの良否判定
- セラミック材料のひび割れ判定
- その他均質材料の内部クラックの発見 等
ポイント
- 加振に当たっては、対象物が自由振動するような拘束条件にて設置する。この時剛体モードの周波数が一次モードの周波数の 1/10 程度になることが望ましい。
- 計測対象を宙吊りとして、自由振動させる
- 上記が難しい場合などはスポンジ等の柔らかい材質のものの上に置く - 内部クラックの振動は、入力依存する場合が多いので、打撃力を調整する。
- 計測に関係しない非線形要素(がた、摩擦)は極力排除する。
- 拘束条件の不安定性や、残存非線形要素により、製品の周波数特性が安定しない場合良品と不良品の判定が難しくなる。
自社の設備や測定ツールを利用した、自動車の評価試験や音響・振動試験(出張測定含む)をお引き受けします。
また、お客様の困り事や課題に対するコンサルティングもお引き受けします。 課題設定から、現象把握、効果確認まで、お客様の解決プロセスをご支援します。
詳しくはこちらのページを参照ください。
最終更新日:2025/06/07
