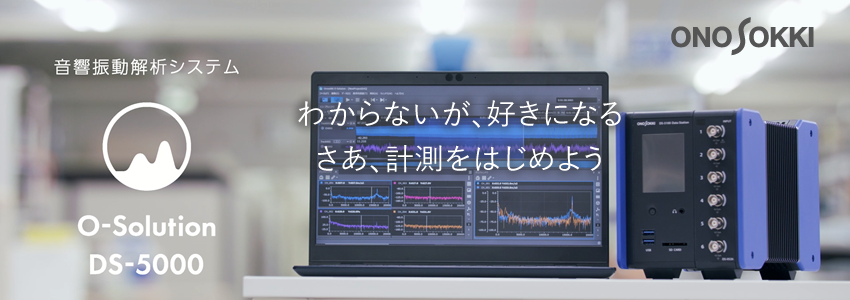両耳効果
両耳効果
今日は、この間ちょっと触れた「両耳効果」について話をしよう。
両耳に入る音の時間差のことや、頭のかたちが関係していることを、前に教えてくれたよね。それから、ステレオの2つのスピーカから等距離のにいるときは、音が真ん中に定位して、どちらかのスピーカに近づいたときに、近いスピーカに音源の定位が移るということだったね。
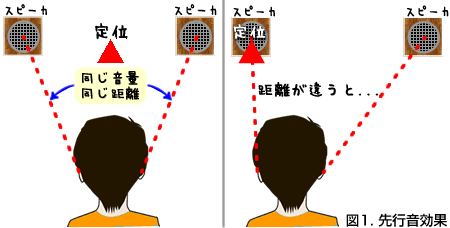
いくつかの音源があっても、真っ先に耳に到達する音に音源の位置を知覚することが「先行音効果」で、その方向が定位できるのは、「両耳効果」のため、と言ったほうがいいかもしれないね。 (図1)
また、空間の拡がりを感じることも頭の両側に耳がついているために知覚する感覚で、これも「両耳効果」とよんだいるんだよ。
また、空間の拡がりを感じることも頭の両側に耳がついているために知覚する感覚で、これも「両耳効果」とよんだいるんだよ。
空間の拡がりってコンサートホールでの響きのことをいってるの?
空間の響きは、片耳を塞いでも感じることはできるだろ。少し専門的になるけど、空間の中での「拡がり感」には、2種類の知覚があることがわかってるんだ。一つは、「音に包まれた感じ」で、こちらの方が空間のひろがりのイメージに近いかな。もう一つは、音源そのものが拡がった感覚で、「みかけの音源の幅」という言い方をするんだよ。両方とも、直接音の後に到来する反射音の構造(方向と時間と大きさ)でその感覚量が変わってくるんだ。 (図2)
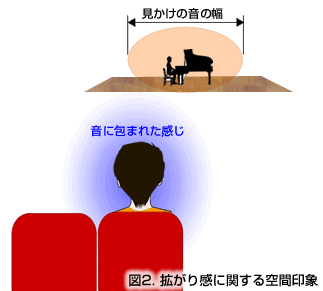
なんだか難しいね。耳が両方についているから、音が来る方向がわかるということはイメージし易いけど。
そうだね。じゃあ、響きがない部屋
(無響室)で、音源が1つのときを考えてみよう。 真正面から音が来たときは、両耳に入る音波に時間的なギャップはないから、真正面に音源があると感じる。 ただ、真後ろからでも同じだから、時間差がないのは、真後ろからの音は真正面からの音と間違うことも多いんだ。
へえー、そうなんだ。真後ろからの音を真正面から来たと間違ってしまうことって、経験したことがないように思うけどね。
普通の部屋では、真後ろからの音以外の、壁や天井からの反射音が後方からの音の情報となっていることが一つの理由だね。もう一つは、音は意味を伴うことがほとんどだから、その音が何の音か、聴いた瞬間に日常的に把握している周囲の環境の情報と重ね判断しているんだね。
音以外に情報がなくて、しかも壁や天井からの反射音がこない実験室で音を呈示する実験は、普段経験してることとは違うということなんだね。
そうだね。でも、こういう実験は、不確定な要因をなるべくなくして、シンプルにしないと、本当のことがわからないからね。1つ1つの実験で明らかにしたことを総合して、現実の環境で起こっていることを説明できることが必要なんだよ。
なるほどね。真正面以外では、どうなの?
「 そうだったね。おとは、人がどれぐらいの角度で音の方向を聴き分けていると思う?
よくわからないけど、10度ぐらいかな?
実は、正面に近い方向では、周波数によって差があるけど1〜3度ぐらいの分解能があるんだ。これは、結構凄いことで、両耳に入る音の時間差は10万分の1秒 (10 μs) くらいしかないんだ。
そんなに細かい角度まで聞き分けることが出来るんだね。正面から離れるとどうなるの?
正面から60度ぐらい横のほうになると、方向定位の精度はかなり落ちて、真横からでは、40度ぐらいの幅でしか感知できないだ。(図3)
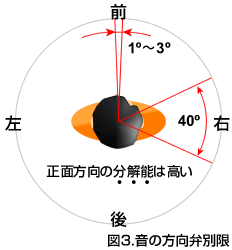
へえー、正面と真横ではそんなに変わってしまうんだね。
それは、前に説明した頭部伝達関数の左右差が真横では大きくなるから、入射角度が多少変わっても、左右差の違いが、正面に近いときの左右差にくらべ、小さくなるからなんだね。それと、もう一つは、人が音の方向を確かめようとするときは、その方向を向くから、正面近くの感度は、自然と高くなっているのかもしれないね。 それと大事なことは、これまで時間差のことしてか話してなかったけど、方向を聴きわける手がかりは、時間差と音圧差の両方なんだ。
音圧差って、左右で回折の仕方が違うから、音圧にも差が生じてくるからなの?
そうだね。2つの手がかりは周波数と関係があって、時間差は、1500 Hz 以下、音圧差は1500 Hz 以上で有効といわれているんだよ。
複雑なんだね。やはり無響室のようなところで、少しずつ解明していくことが必要なんだね。
そうだね。前にカクテルパーティ効果のことも話したよね。これも、選択的に聞き取るために、両耳によって、方向を判断できることが寄与しているんだ。このような方向定位の研究は、ロボット工学など応用範囲は広いんだよ。