

測定範囲は変わりますが、計測可能です。計測可能な範囲は次のような条件により変わります。
わかりやすい例として反射マークを半分にする事を考えてみましょう。単純に考えて、反射マークを半分にするということは反射光量も半分になるということで受光感度が悪くなることになります。従って規定サイズ(12×12 mm)の反射マークと同等光量を得るには測定距離を短くするしかなく、規定サイズの反射面積をS、規定の最大計測距離をLmaxとすると次図より ;
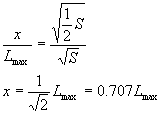 |
となります。
つまり最大計測距離は規定サイズの反射マーク使用時に比べて 約70%に近づける必要があります。
|
次図の様に、回転速度をn (r/min)、回転中心から反射マークまでの距離を r とすれば、Δd 幅の反射マークが有効反射している時間 Δt は ;
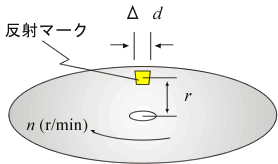
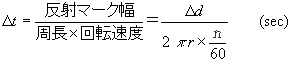
となります。Δt の最小時間= Δt min 受信可能最小応答時間)はセンサーや機器により異なり、目安として下表の様になります。
| 機種名 | 最小応答時間 Δt min( ms ) |
|---|---|
| HT-4100 | 0.2 |
| HT-5100/5200 | 0.2 |
| LG-9 | 0.6 |
| LG-930 | 0.5 |
| FG-1300 | 0.1 |
| PP-940 | 0.05 |
応答時間 Δt min より計測可能な最大回転速度を表すと;
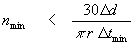
さらに反射光 OFF の時間(反射マークが無い部分)も最低同程度必要なので最大回転速度を表す式は ;
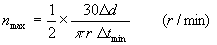
したがって、反射マーク( Δd )が半分になると最大回転速度(![]() )は半分になります。以上は、あくまで計算上での話で、実際はもう少し余裕を見込んでおく必要があります。
)は半分になります。以上は、あくまで計算上での話で、実際はもう少し余裕を見込んでおく必要があります。
測定最大回転速度を大きくするには
最大回転速度を高くするためには上式のΔdを大きくすれば良いことも分かります。つまり反射マークを隙間を空けないで2枚、3枚つなげて貼ることで最大 回転速度は2倍、3倍にすることができます。