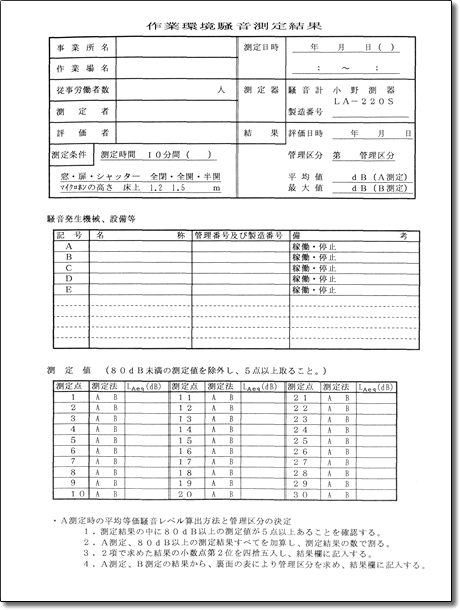労働安全衛生規則の抜粋(騒音関係)
(産業医の選任)
第13条 法第13条の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
産業医を選任すべき事項が発生した日から14日以内に選任すること。 2
常時1000人以上の労働者を使用する事業場または次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場に合っては、その事業場に専属の者を選任すること。
(イからト 略)
チ: ボイラー製造等強烈な音を発する場所における業務
(リからカ 略)
常時3000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任すること。
事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、様式第4号による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、学校保健法(昭和33年法律第五十六号)第16条の規定により任命し、または委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととさせたものについては、この限りでない。
(第3項 略)
(定期健康診断)
第44条
事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目に付いて医師による健康診断を行わなければならない。
既往歴および業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の調査
身長、体重、視力および聴力の検査
胸部エックス線検査および喀痰検査
血圧の測定 6. 貧血検査
肝機能検査
血中脂質検査
尿検査
心電図検査
(第2項から第4項 略)
第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る)は、35歳未満の者および36歳以上40歳未満の者に付いては、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1000ヘルツまたは4000ヘルツの音に係わる聴力を除く)の検査をもって代えることができる。
(特定業務従事者の健康診断)
第45条
事業者は、第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際および6月以内毎に1回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目に付いて医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目に付いては、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。
前項の健康診断(定期のものに限る)は、前回の健康診断において第44条第1項第6号から第8号までおよび第10号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、第1項の規定にかかわらず、医師が必要でない認めるときは、当該項目の全部または1部を省略して行うことができる。
第1項の健康診断(定期のものに限る)の項目のうち第44条第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者または35歳未満の者および36歳以上40歳未満の者については、第1項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1000ヘルツまたは4000ヘルツの音に係わる聴力を除く)の検査をもって代えることができる。
(有害原因の除去)
第576条
事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気または粉じんを発散し、有害な光線または超音波にさらされ、騒音または振動を発し、病原体によって汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法または機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。
(騒音を発する場所の明示等)
第583条の2
事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によって明示するなどの措置を講ずるものとする。
(騒音伝ぱの防止)
第584条 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
第588条 令第21条第3号の労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。
鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械または器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場
ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り、または板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取りおよび板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く)を行う屋内作業場
動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造または成型の業務を行う屋内作業場
タンブラーによる金属製品の研摩または砂落しの業務を行なう屋内作業場
動力によりチェーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行う屋内作業場
ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場
チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場
多筒抄紙機により紙をすく業務を行う屋内作業場
前各号に掲げるもののほか、労働大臣が定める屋内作業場
(騒音の測定等)
第590条 事業者は第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内毎に1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
測定日時
測定方法
測定個所
測定条件
測定結果
測定を実施した者の氏名
測定結果に基づき改善措置を講じたときは、当該措置の概要
第590条
事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、または当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
前条第2項の規定は、前項の規定による測定を行った場合に準用する。
(騒音障害防止用の保護具)
第595条
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。
(保護具の数等)
第596条 事業者は、前3条に規定する保護具に付いては、同時に就労する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
(労働者の使用義務)
第597条
第593条から第595条までに規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
作業環境測定基準の一部改正(騒音関係)
(騒音の測定)
第4条
令第21条第3号の屋内作場(労働安全衛生規則第588条各号に掲げる屋内作業場に限る)における等価騒音レベルの測定は、次に定めるところによらなければならない。
測定点は、単位作業場所の床面上に6メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上120センチメートル以上150センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な場所を除く)とすること。ただし、単位作業場所における騒音レベルがほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係わる交点は、当該作業場所の床面上に6メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線の交点とすることができる。
前号の規定に係わらず、同号の規定により測定点が5に満たないこととなる場合にあっても、測定点は、単位作業場所について5点以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場所であって、当該単位作業場所における騒音レベルがほぼ均一であることが明らかなときは、この限りでない。
音源に接近する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては前2号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、騒音レベルがもっとも大きくなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。
測定は、次ぎに定めるところによること。
イ:
測定に用いる機器(以下「騒音計」という)は日本工業規格C1502(普通騒音計)に定める規格に適合するものまたはこれと同等以上の性能を有するものであること。
ロ: 騒音計の周波数補正回路のA特性で行うこと。
ハ:(削除)
一つの測定点における測定時間は10分間以上の継続した時間とすること。
騒音障害防止のためのガイドラインから抜粋した別表
別表1
- 鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械または器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場
-
ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り、または板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取りおよび板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く)を行う屋内作業場
- 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造または成型を行う屋内作業場
- タンブラーによる金属製品の研摩または砂落しの業務を行なう屋内作業場
- 動力によりチェーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行う屋内作業場
- ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場
- チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場
- 多筒抄紙機により紙をすく業務を行う屋内作業場
別表2
- インパクトレンチ、ナットランナー、電動ドライバー等を用い、ボルト、ナット等の締め付け、取り外しの作業を行う作業場
- ショットブラストにより金属の研磨の業務を行う作業場
- 携帯用研削盤、ベルトグラインダー、チッピングハンマー等を用いて金属の表面の研削または研磨の業務を行う作業場
- 動力プレス(油圧プレスおよびプレスブレーキを除く)により、鋼板の曲げ、絞り、せん断等の業務を行う作業場
- シャーにより鋼板を連続的に切断する業務を行う作業場
- 動力により鋼線を切断し、釘、ボルト等の連続的な製造の業務を行う作業場
- 金属を溶融し、鋳鉄製品、合金製品等の成型の業務を行う作業場
- 高圧酸素ガスにより、鋼材の溶断の業務を行う作業場
- 鋼材、金属製品等のロール搬送等の業務を行う作業場
- 乾燥したガラス原料を振動フィーダーで搬送する業務を行う作業場
- 鋼管をスキッド上で検査する業務を行う作業場
- 動力巻取り機により鋼板、線材を巻取る業務を行う作業場
- ハンマーを用いて金属の打撃または成型の業務を行う作業場
- 圧縮空気を用いて溶融金属を吹き付ける業務を行う作業場
- ガスバーナーにより金属表面の傷を取る業務を行う作業場
- 丸のこ盤を用いて金属を切断する業務を行う作業場
- 内燃機関の製造工場または修理工場で、内燃機関の試運転の業務を行う作業場
- 動力により駆動する回転砥石を用いて、のこ歯を目立てする業務を行う作業場
- 衝撃式造形機を用いて砂型を造形する業務を行う作業場
- コンクリートパネル等を製造する工程において、テーブルバイブレータにより締め固めの業務を行う作業場
- 振動式型ばらし機を用いて砂型より鋳物を取り出す業務を行う作業場
- 動力によりガスケットを剥離する業務を行う作業場
- 瓶、ブリキかん等の製造、充填、冷却、ラベル表示、洗浄等の業務を行う作業場
- 射出成型機を用いてプラスチックの押し出し、切断の業務を行う作業場
- プラスチック原料等を動力により混合する業務を行う作業場
- 味噌製造工程において動力機械により大豆の選別の業務を行う作業場
- ロール機を用いてゴムを練る業務を行う作業場
- ゴムホースを製造する工程において、ホース内の内紙を編上機により編み上げる業務を行う作業場
- 織機を用いてガラス繊維等原糸を織布する業務を行う作業場
- ダブルツインスター等高速回転の機械を用いて、ねん糸または加工糸の製造の業務を行う作業場
- カップ成型機により、紙カップを成型する業務を行う作業場
- モノタイプ、キャスター等を用いて、活字の鋳造の業務を行う作業場
- コルゲータマシンによりダンボール製造の業務を行う作業場
- 動力により、原紙、ダンボール紙等の連続的な折り曲げまたは切断の業務を行う作業場
- 高速輪転機により印刷の業務を行う作業場
- 高圧水により鋼管の検査の業務を行う作業場
- 高圧リムーバを用いてICパッケージのバリ取りの業務を行う作業場
- 圧縮空気を吹き付けることにより、物の選抜、取りだし、剥離、乾燥等の業務を行う作業場
- 乾燥設備を使用する業務を行う作業場
- 電気炉、ボイラーまたはエアコンプレッサーの運転業務を行う作業場
- ディーゼルエンジンにより発電の業務を行う作業場
- 多数の機械を集中して使用することにより製造、加工または搬送の業務を行う作業場
- 岩石または鉱物を動力により破砕し、または粉砕する業務を行う作業場
- 振動式スクリーンを用いて、土石をふるい分ける業務を行う作業場
- 裁断機により石材を裁断する業務を行う作業場
- 車両系建設機械を用いて掘削または積み込みの業務を行う坑内の作業場
- さく岩機、コーキングハンマー、スケーリングハンマ、コンクリートブレーカ等圧縮空気により駆動される手持ち動力工具を取り扱う業務を行う作業場
- コンクリートカッタを用いて道路舗装のアスファルト等を切断する業務を行う作業場
- チェーンソーまたは刈払機を用いて立木の伐採、草木の刈払い等の業務を行う作業場
- 丸のこ盤、帯のこ盤等木材加工用機械を用いて木材を切断する業務を行う作業場
- 水圧バーカーまたはヘッドバーカーにより、木材を削皮する業務を行う作業場
- 空港の駐機場所において、飛行機への指示誘導、給油、荷物の積み込み等の業務を行う作業場
[次ページへ続く]